当ブログはプロモーションを含みます
小学6年生の我が息子、小5の終わりの2月から通っていた早稲アカを6月で辞めました。
半年ももたなかったね・・・
塾が嫌過ぎてサボる
息子は、小学2年生の夏頃から色々な塾に通っていました。
【関連カテゴリー】塾のコト
小学4年生くらいまでは、まぁ問題なく通っていたのですが、小学5年生からチラホラサボり始め、中学受検撤退。
小学6年生からは心機一転、高校受験を見据えた早稲アカに転塾し、難易度もグッと下がり、通塾日数も時間も短くなったにも関わらず、サボりが酷くなりました。
私にとっても塾のある日は、そりゃもうストレスでした。
「ちゃんと塾に間に合う時間に帰ってくるだろうか」と毎回ドキドキ。
そして帰ってこず、塾に連絡したりラジバンダリ。
さすがに月謝代が無駄過ぎるし、私もストレスで血圧上がるし、で、退塾することにしました。
塾を辞める時の退塾理由や伝え方
我が子、こんな感じでサボることが多く、ある意味問題児だった為(授業中に騒いで他人に迷惑をかける系の問題児ではない)、先生もある程度わかっていたと思います。
退塾の電話をする前に、塾の先生からも電話を頂いていたし、サボりが酷い場合は退塾も考えている、ということは伝えていました。
なもんで、退塾理由は言わずもがな。
「勉強嫌い、塾嫌い、やる気ない」
もう、ストレートに包み隠さず伝えました。
ついでに私は早稲アカのカリキュラムが好きで継続させたかった旨も伝えました。
ホントね、私は早稲アカのシステム大好き。
システマチックでとてもイイ!
あのカリキュラムをキチンとやりこなせれば成績あがるよ。
普通の子は嫌でもサボらない
電話で退塾する旨を伝えた後は、実際に塾に赴き退塾手続きをします。
その際に、事務の先生(喋っているだけでシゴデキな人と感じる)と雑談した時のコト。
「あー、塾に行きたくないな」と思っても、実際にサボる子はいない
そうですorz
親に怒られるくらいなら、行きたくない塾に行った方がマシなんだとか。
我が子は、塾に行くくらいなら喧嘩上等!という勢いです。
もうね、全力拒否よ。
ある意味、自分の意見をしっかり主張できる健全な家庭環境と言うべきかヽ(´Д`;)ノ
夏期講習がない夏休み
そんなこんなで6月に塾を辞め(6月も移動教室やらサボりやらで殆ど行っていない)、「塾の夏期講習」がない夏休みとなりました。
これは小学1年生振りだな。
自由で充実した夏を過ごしている息子。
私もストレスがかなり軽減され、血圧も下がりました(๑•᎑•๑)
今は細々と私が用意したドリルで勉強している日々です。
詳細はまた次回。












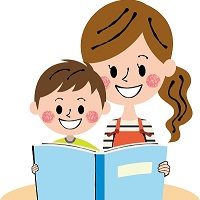









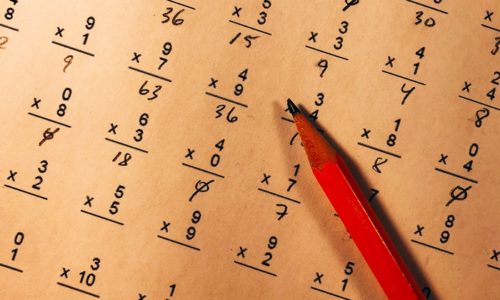
この記事へのコメントはありません。